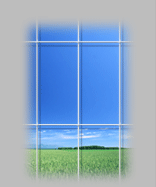窓、ガラス、ウィンドウ・フィルムに関係した用語を集めて解説をつけました。
「フィルムナビ」や「事例研究」の中に出てきた用語で意味がわからないときにお使いください。
用語は50音順に並べられています。
【あ行】
網入りガラス(あみいりがらす)
金網や金属線を中にはさみ込んだ板ガラス。ガラスの中に、格子やひし形、きっ甲形などの金属製網を封入した板ガラスのことで、火災時に延焼、類焼を防ぐといわれ、乙種防火戸などに使用される。反面、防犯効果はあまり期待できないともいわれる。ワイヤーガラス、網入り板ガラスともいわれる。
合わせガラス(あわせがらす)
2枚のガラスを接着し、貫通しにくく、飛散防止効果の高い安全ガラス。
内貼り(うちばり)
一般的なフィルムは室内側に貼り、これを内貼りという。通常のフィルムは接着面で紫外線カットし本体の劣化を防ぐ。このため、外から貼ることはできない。
塩ビ・塩化ビニル(えんび・えんかびにる)
PVC、Polyvinyl chloride、ポリ塩化ビニルなど表現される。43%の石油製品と53%の塩を原料として成るプラスチックスで、他の材料と比べても、原料やエネルギ−の消費がより少ないが、ダイオキシンなどを伴うため、環境負荷を伴う側面もある。
【か行】
可視光線(かしこうせん)
太陽光線のうち、人間の目に見える波長領域380〜780nmの光。太陽エネルギーの約45%を占めている。可視光線の透過率が高いほど、ガラスの透明性・採光性は保たれる。
型板ガラス(かたいたがらす)
ガラス表面に凹凸があり、不透明にしたガラス。
環境負荷(かんきょうふか)
環境に与えるマイナスの影響、ウインドウ・フィルムの場合は主に室内環境維持に伴う熱エネルギー、CO2のことを示す。
官民合同会議(かんみんごうどうかいぎ)
建物への侵入犯罪の防止を図るため、平成14年11月に「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が設置された。「防犯性能の高い建物部品目録」を平成16年4月発表。
傷防止(きずぼうし)
貼り付ける対象物の保護を目的とし、本体の損傷を抑制する。性能には限度があるが、ガラスに限るものではない。この用途には外貼りや樹脂用などの機能が必要となる。
吸収率(きゅうしゅうりつ)
日射光の一部はガラスに吸収され、熱として再放出される。これを吸収という。吸収率は光学特性を示す指標で、フィルムでは3mm厚のフロートガラスに貼付した状態での実測値。
クレセント(くれせんと)
アルミサッシなどの窓に取り付けられている締め金具のこと。
けつろ(結露)
窓ガラス・壁など冷えた物体の表面に、空気中の水蒸気が凝縮し水滴となって付着する現象。ガラス表面が露点温度に達すると曇り、さらに進んだ状態が結露となる。これに防ぐためには、断熱するか表面に親水性を持たせる方法などがある。結露を完全に防ぐには断熱もしくは加熱することが必要。
国家技能検定試験(こっかぎのうけんていしけん)
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)に基づき、技能に関する一定の基準を設け、労働者の有する技能がその基準に達しているか否かを判断し、これを公証するもの。昭和34年度より実施されている。平成14年6月11日厚生労働省令第77号の定めるところにより、日本ウインドウ・フィルム工業会は、職業能力開発促進法47条第1項の規定に基づく厚生労働大臣指定試験機関として指定を受け、ガラス用フィルム施工職種の技能検定試験1級及び2級を実施している。1級の合格者には、厚生労働大臣名の合格証書が交付され、2級の合格者には、日本ウインドウ・フィルム工業会の理事長名の合格証書が交付され、いずれも技能士と称することができる。
【さ行】
CPマーク(しーぴーまーく)
防犯部品の表示マークで、「防犯性能の高い建物部品」の普及促進を行うため、共通呼称(防犯建物部品)とシンボルマークを官民合同会議にて作成したもの。Crime Prevenetion(防犯)
紫外線(しがいせん)
太陽光線のうち、人間の目には見えない波長領域280〜380nmの光。人体への悪影響や、室内調度品の退色などの原因となる。
紙管(しかん)
一般的にフィルムはロール状に巻かれており、この芯材を示すもので、紙以外の材質も多く使われている。
JIS-A5759(じす)
規格名称:建築窓ガラス用フィルム 事務所、店舗、住宅など(以下建築物という)の窓ガラスに貼付し、屋内の冷房及び暖房効果を高める為の日射遮蔽用フィルム、及び衝突、地震、爆発によって、建築物の窓ガラスが飛散落下することを軽減するためのガラス飛散防止フィルムならびにその両方を兼ねた日射遮蔽・ガラス飛散防止用フィルムについての規定。
遮熱(しゃねつ)
本来は軒や庇、格子、樹木などを用いて光をさえぎることを示す。フィルムの場合は、熱線反射や熱線吸収方式による赤外線領域の波長のコントロールを意味し、省エネフィルムなどとも呼ばれている。
遮蔽係数(しゃへいけいすう)
3mmフロートガラスを1.00とした場合、これにフィルムを貼付した場合に室内に入り込む日射量の割合を示した値。この値が小さいほど断熱性能が優れている。
樹脂ガラス(じゅしがらす)
造語でガラス以外のポリカーボネイトやアクリル材などでガラスの替わりに使用される樹脂製板。
省エネ(しょうえね)
赤外線を反射若しくは吸収発散することで、特に冷房時の熱負荷を低減する。遮熱はフィルムの最も優れた性能のひとつ。透明タイプと高性能タイプがある。透明タイプは遮蔽係数が0.85未満で、可視光線透過率70%以上、高性能タイプは遮蔽係数が0.4未満の高性能なもので、主に非透明。
水泡・気泡(すいほう・きほう)
施工時の施工液が残りフィルムがレンズ状になったものを水泡、同様に空気が入ったものを気泡という。施工直後は通常透明で、2、3日すると施工液が下のほうに集まり小さな泡が発生することがあり、これを水泡という。ある条件化の正常な状態で時間がたてば無くなる。気泡の場合は時間がたっても変化は見られない。
赤外線(せきがいせん)
太陽光線のうち、人間の目には見えない波長領域780〜2,100nmの光。太陽エネルギーの50%を占める熱的作用の大きい光線。
外貼り(そとばり)
耐久性のある基材を使用し、屋外に施工可能なもの。通常のフィルムは接着面で紫外線カットし本体の劣化を防いでいるため、ガラスの外側に貼るとすぐに劣化する。耐摩耗性をアップさせるため、表面に特種コーティングしたものと、表面にキズ防止の処理がされていないものがある。
【た行】
耐貫通(たいかんつう)
衝撃エネルギーに耐え、落球物当が貫通(ガラスに穴が開く)に耐える性能評価で、その目的(計測方法により)によって基準値は異なる。
ダイレクトゲイン(だいれくとげいん)
南側に大きな開口部をとって、冬の斜めから差し込む日射を室内に入れ、その熱を床や壁の蓄熱体に蓄え、夜、部屋が寒くなると、その蓄熱体からの放熱で部屋が暖められるという仕組み。
断熱(だんねつ)
外部との熱の出入りをさえぎること。熱還流率、伝熱係数などによって性能表示される。室内の熱を逃がさない効果をしめすもので、数値が少ないほど暖房負荷低減に寄与する。
着色(ちゃくしょく)
フィルムの着色の方法には、顔料、染色、原着、色糊がある。顔料コートは顔料をポリエステルフィルムの表面にコーティングして着色したものコーティングフィルムなどと呼ぶ耐候性が高いが透明感がない。 染色は、染料で染色したフィルムのこと、透明度が良く。 原着フィルムはフィルムの原料の段階で染料を混入したもので、染色フィルムに対して色あせしにくい。 色糊フィルムは粘着剤に染料、もしくは顔料を混入したものコストが安いが色むら等品質が悪く、量販店などに多い。
突合せ(つきあわせ)
フィルムをフィルムの幅より大きなガラス面に貼り付ける場合は、フィルムを貼り合わせる必要があるが、この合わせる部分を「付き合わせ」という。突き合わせ部分は、フィルムの端部同士を突き合わせる。
電磁波防止(でんじはぼうし)
電磁波には、大きく分けて高周波と低周波があり、携帯電話、電子レンジ、レーダー、TV電波などが前者で、家電機器や送電線が後者。電磁波の単位は、電場(V/m)や磁場(GまたはmG)。電磁波を室内に侵入させない効果を電磁波シールド効果と言い、コンピュータシステムの障害防止、携帯電話のコントロール、また人体への影響を抑えるなど、電磁波防止は最近注目されている。FNCではEMIシールド性能300MHzでの遮断率が30dB以上あることを性能基準にしている。
透過率(とうかりつ)
光学特性を示す指標で、特定領域(紫外線:280〜380nm、可視光線380〜780nm、日射:350〜2,100nm)の光の透過率。フィルムでは3mm厚のフロートガラスに貼付した状態での実測値。
透明・不透明(とうめい・ふとうめい)
FNCでは、目隠しやデザインフィルム以外で可視光線透過率70%以上のフィルムを透明フィルムと定義し、それ以外を不透明としている。
トンネル現象(とんねるげんしょう)
粘着面と剥離紙との間に隙間が生じる際に、糊ずれが生じ白くなり貼り付け後も消えなくなる現象で、ツノとも呼ばれる場合もある。カットしたフィルムを長時間丸めて置くと生じやすい。
【な行】
日射(にっしゃ)
太陽光線で紫外線、赤外線を含む波長領域350〜2,100nmの光をしめす。
日照調整(にっしょうちょうせい)
軒や庇、格子、樹木などを用いて日射を調整すること。フィルムの場合は遮熱フィルムや着色フィルムを示す。
日本ウインドウフィルム工業会(にほんういんどうふぃるむこうぎょうかい)
フィルム製造者および輸入総代理店からなる業界組織。下部組織にJGFA(日本ガラスフィルム工事業協会)、JCAA(日本自動車用フィルム施工店会)、STU(自動車硝子安全施工事業協同組合)がある。厚生労働大臣指定試験機関としてフィルム施工技能検定を司っている。
日本ガラスフィルム工事業協会(にほんがらすふぃるむこうじきょうかい)
JGFA(日本ガラスフィルム工事業協会)は日本ウインドウフィルム工業会の下部団体で、施工会社組織。
熱貫流率(k値)(ねつかんりゅうりつ)
3mmフロートガラスにフィルムを貼付した場合の断熱性能を表しており、ガラスの両側の温度差を1℃とした場合、ガラス1m2・1時間当たりの熱伝達量(単位:w/m2k)。この値が小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能が優れている。
熱割れ(ねつわれ)
窓ガラスに日光が当たると照射された部分とその他の部分(サッシュにのみこまれた周辺部、影の部分等)に温度差が生じ、ある強度を越えるとエッジよりヒビが発生する現象を言う。
粘着性能(ねんちゃくせいのう)
フィルムのガラスとの接着力を示すもので、JIS-A5759の規格によるサンプルの90度引っ張り測定による。
【は行】
ハードコート(はーどこーと)
フィルム基材そのものは傷付き易いので、耐摩耗性をアップさせるため表面に特種コーティングしたもの。人が接触する部分には一般的には必須。
白濁現象(はくだくげんしょう)
施工後フィルム面が白く濁ることをいう。施工直後に施工液が集まり白く濁る場合と、 圧着の不均衡により空気が糊面に細かく入り込んでいる場合とがあり、前者は正常反応で時間がたてば無くなるが、後者の場合は時間の変化はない。
剥離紙(はくりし)
フィルム本体に糊が塗りつけてあり、空気に触れ劣化したり汚れたりすることを防ぐためのカバーを剥離紙またはライナーという。
反射防止(はんしゃぼうし)
ガラスの室外面に日光が当たり、反射することで光公害が発生することがあります。反射防止フィルムとは、ガラス室外面の貼り付ける事により光を乱反射させ、反射を抑える働きをする。
反射率(はんしゃりつ)
光学特性を示す指標で、日射光の反射率を示す。フィルムでは3mm厚のフロートガラスに貼付した状態での実測値。
光触媒(ひかりしょくばい)
光触媒は太陽や蛍光灯などの光が当たると、その表面で強力な酸化力が生まれ、接触してくる有機化合物や細菌などの有害物質を除去することができる環境浄化材料。
飛散防止性能(ひさんぼうしせいのう)
ガラスにウインドウ・フィルムを貼付け、破損した場合でも、破片が飛び散らないようにすること。飛散防止性能試験JIS A 5759には、ガラス面に物体が衝突した場合の安全性に関するA法(衝撃破壊試験)と、地震などによりガラスが歪んだ場合の安全性に関するB法(層間変位破壊試験)とがある。
複層ガラス(ふくそうがらす)
2枚のガラスの間の中空層で、断熱効果を高めたガラス。ペアーガラスとも言う。
フロートガラス(ふろーとがらす)
普通ガラス、両面が平滑で透明なガラス。5mmガラスの場合可視光線透過率90%程度
防虫性能(ぼうちゅうせいのう)
夜間に照明に寄ってくる虫の反応する波長をカットするもので、照明器具に貼っても効果的。透明タイプと高性能タイプがあり、透明タイプは飛翔昆虫誘引阻止率50%以上もので、可視光線透過率が70%以上、高性能タイプは飛翔昆虫誘引阻止率 80%以上で非透明。
防犯性能(ぼうはんせいのう)
空き巣に対する抵抗力を示すもので、我が国内では「官民合同会議」の防犯性能試験がその基準となっている。試験は打ち破り、コジ破り、焼き破りの3種をおこない、全ての基準を満たすものを防犯性能認定製品としており、住宅性能表示などにも採用されている。
補助ロック(ほじょろっく)
アルミサッシのクレセント以外の締め金具のことで、補助錠設置は防犯フィルムのCPマーク貼り付け基準となっている。
ポリエステル(ぽりえすてる)
ポリエステル(PET,Polyester)とは多価カルボン酸(ジカルボン酸)とポリアルコール(ジオール)との重縮合体である。
ポリカーボネイト(ぽりかーぼねいと)
PVBよりも硬く強靭な樹脂。ガラスの200倍、アクリルの30倍以上の強度がある。重さも軽くガラスの半分。
【ま行】
水抜け(みずぬけ)
貼り付け後は水分の蒸発に時間がかかるほか、施工後の水玉の原因となりやすいため、圧着時に十分に水を吐き出す必要がある。
目隠しフィルム(めかくしふぃるむ)
外からの視野を遮り室内を見え難くする。すりガラス調、マット調、デザイン調などがあり、JIS A 5759第2種飛散防止に適合しているものと、適合品ではないがPVCを使用し風合いは変わらないものがある。
【や行】
誘引阻止率(ゆういんそしりつ)
日本環境動物昆虫学会、日本衛生動物学会でも発表されたフィールド試験方法である防虫試験法(オプトロン法)に基づく、フィルムの防虫効果の指標。ガラス板のみの場合と比較したこの数値が大きいほど、防虫性能が優れている。
養生(ようじょう)
養生(ようじょう)とは、工事中に床、家具等が傷ついたり、濡れないように覆いなどを掛けて保護すること。
養生期間(ようじょうきかん)
フィルムの貼り付け時に使う施工液の水分が完全に蒸発するまでの期間を示すもので、施工技術、温湿度環境、フィルムの構成などの条件によって異なる。